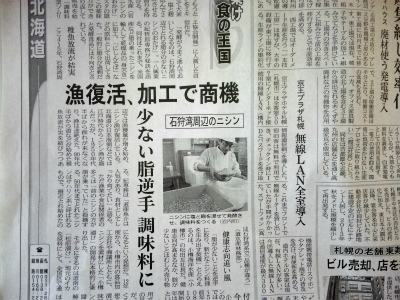今ではすっかり定着した道の駅スタンプラリー。スタンプを押すことを目的とし、北海道を旅行する方も多いと思います。
岩内町の道の駅『たら丸館』は、北海道の道の駅の中で、建物としては小さい存在です。ほかの道の駅が、物販を中心とした商業施設になっているのに対し、岩内の道の駅は物販のスペースはほんの少し。最悪なのは、トイレが建物の中になくて、トイレ、駐車場、情報施設3つが分散しているということです。
ほとんどの皆様は、この分散において、不満を感じられることでしょう。地元でも現在の道の駅の存在を疑問視する声もたくさん出ています。大きな建物に作り変えようという声もあります。
岩内の道の駅の認定は全道で14番目という早いものでした。後から認定された道の駅は、成功事例をもとに、いろいろな特色を打ち出しています。それゆえ、それらと比較すると岩内の道の駅は貧弱に感じることでしょう。
地元では、大きな施設に作り替え、販売をもっと充実させるべきだという意見と、他の店に迷惑がかかるから販売はしなくてもいいという意見もあります。この点については、より多くの人たちとの議論を経たうえで、今後の方針を決めればいいと思います。
旅行先の町のことを、道の駅しか知らないというのも寂しいものです。旅行者には、せっかく来ていただいたのだから、道の駅以外にも立ち寄ってもらうべき魅力あるお店や商品、場所を持つ必要性があると思います。またそれらの情報発信が必要だと私は思います。
何より一番大切な事は、旅行者に対する暖かい気持ちを持つ事。そして町そのものの魅力とそこに住む人の魅力が大切だと私は思っています。と言う私自身もまだまだ発展途上の人間ですので、今述べた生意気な発言はご容赦ください。
岩内を愛してくださる皆様、岩内に立ち寄ってくださる皆様は、岩内の道の駅がどのように変わるといいか、ご意見があったらお知らせください。私のブログへの投稿でもいいですし、道の駅スタッフでもかまいません。