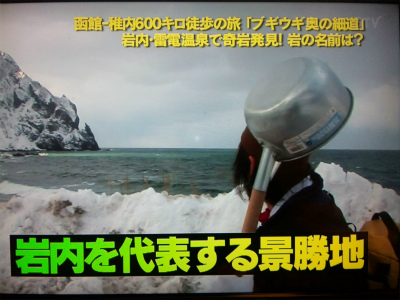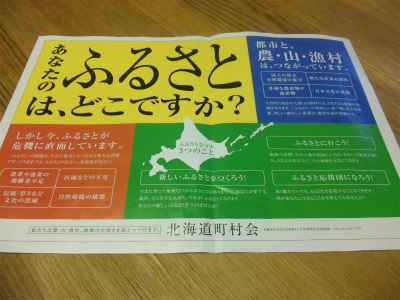平成23年の12月から24年1月の日曜日は、岩内町のスキーに関する事を、昔を振り返りながら書かせていただきました。書いていると、当時の雪の中で遊んだ記憶がフラッシュバックしてきました。今日は、まだ小学低学年だった頃のそり遊びについて書かせていただきます。
大浜の「いなおの坂」と言って、わかる方は、40代後半の年齢まででしょうか。東山のお墓から浜に向かって、大きなカーブを描きながら下ってくる坂を、私たちは通称「いなおの坂」と呼んでいました。国道229号線との交差する場所に「いなお呉服店」というお店があったからです。
お墓のところには漁業協同組合の無線局がありました。そこから20mほどは、とても急な斜面になっていて、そこからそりで滑り、車道に出て、そのまま滑り下りるコース。その他、車道に出てから、また左右の崖に落ちていくというコースがありました。
それらを単独で滑るのはもちろんのこと、そりを二つ、三つとつなげて滑ったり、10以上のソリをつなげることもしました。そうすると、カーブでは後ろのそりが、思いっきり振られて転倒するなんて事も。2つのつなげたソリ同士で競争するときは、コーナリングのテクニックが大切になります。
学校から帰ってくると、近所から子供たちが集まり、だれともなく、そりを連結しようという話になったり。競争のルールも、仕切り役がいて、小さな子は大きな子の間に挟んで、振り落とされないようかばったり。そんなことが自然にできて遊んでいました。
コースは自動車の道路なのですが、自動車の交通量が少ない時代です。冬は今のように除雪が行き届いておらず、もっぱら、そり、スキーの場所になっていました。たまに1時間に1台程度トラックが来ると、数十人の子供たちが、一斉にその行方を見守ります。
着ているものは、今のようなナイロン系ではなく、厚手の綿やウールなので、濡れてくるととても冷いのです。しかし、帰るのが惜しい気持ちの方が上回っていました。良き思い出です。
ちなみに、「いなお呉服店」は数年前に取り壊され、今は更地になっています。坂自体も、当時は歩道もなく、砂利道でしたが、今は側面をきちんとコンクリートで固めた立派な道路になっています。ここで遊んだ事を覚えている方はいらっしゃいます?