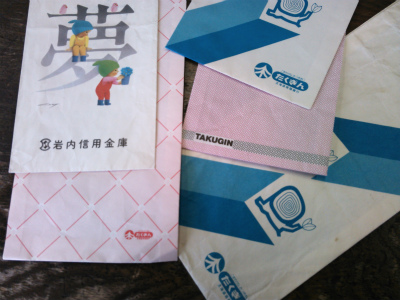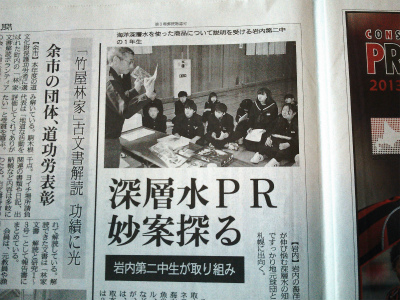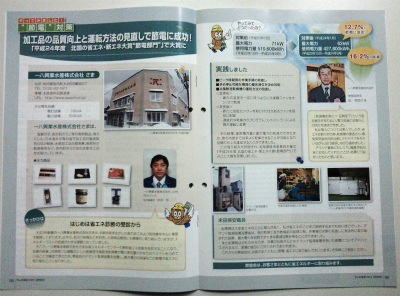タイトルをお読みになって、私が自費出版したと勘違いしないでください。私は学生時代から国語の点数が悪く、ましてや歴史的な背景がある古文や言葉の変化などは、全くダメでした。
出版したのは、幼少から高校まで岩内で育ち、岩内高校で12年間国語の教諭として教えられていた、見野久幸さん。写真は北海道新聞後志版(2013年10月30日付)に掲載されていたものです。この「岩内方言集」の記事は、2日後にも別の角度から紹介されるという異例の取り扱い。それほどの内容だと思います。
私も新聞に出たその日、岩内町の小林書店に行きましたが、すでに売り切れ。2日後にまた入荷しますと言われました。購入してびっくりしたのが、その内容の濃さです。B5版で383ページにも及びます。読んでいくと、当たり前のように使っている言葉から、今は使わないよというものまで詳細に記されています。
見野先生が岩内弁に興味を持ったのは、同じ北海道でも岩内はちょっと違うぞと思ったからではないでしょうか。実際、今の子供たちはほとんど使いませんが、「アヤ」という言葉は岩内では「バカ」を意味します。でも、すぐ隣の共和町や神恵内村の友人は使いませんでした。などなど、岩内出身の皆様、ぜひ岩内に帰省の際は、小林書店で「岩内方言集」をお求めください。税込900円です。
ついでに、お正月用の数の子、釣たらこ等も一八でお求めを・・・・