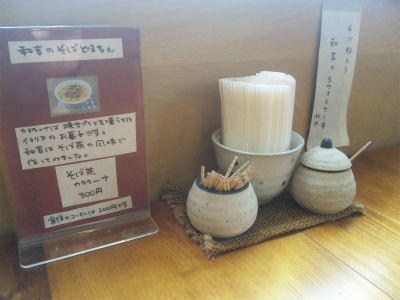日本海岩内海洋深層水は、岩内町地場産業サポートセンターという場所で給水することができます。そこの施設は、研究機関も備わっていて、蓄養のいけすがあって、そこに魚の稚魚がいたり、昆布があったりします。
毎年、小学3年生の子供たちが、社会見学として、この施設を訪れて勉強をしています。その児童たちが見学した事を、新聞のような形でまとめたものが、サポートセンターに張ってあります。
いずれも力作ぞろいで、大人が見過ごしてしまう事を、注意深く表現していたりするのが面白いです。このような社会見学では、興味のある部分が、子供によって違いがあります。そうでなくては面白くないですよね。
いろんな考え方、いろんな興味を持つ人がいてこの社会は成り立っています。食べ物の好みも人それぞれ。この子たちの新聞を見ていると、将来、どんな大人になるのだろうか?とワクワクしてきます。
一度、子供たちの作品をご覧ください。岩内町地場産業サポートセンターです。お役人ですので、土日祝日は休業です。