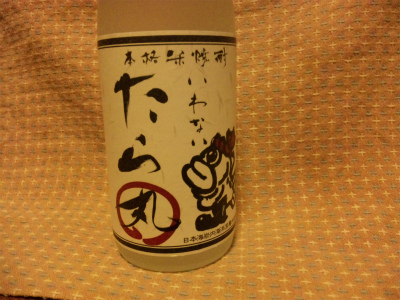先月から毎週日曜日は岩内のスキーの話題を特集しています。今日は当時の学校のスキー授業についてです。
1970年代、私が中学高校時代、3学期の体育にはスキー授業がありました。体が小さく、他のスポーツでは、常に皆の足を引っ張っていた私です。友達はそんな私にスキーだけは一目を置いてくれました。
第一中学校でのスキー授業は、校舎の裏側の20mほどの斜面を使うのが数回。その後一週間の体育の授業を一日にまとめ、午前中1時間か2時間授業をしてから、バスで円山に行き、スキー授業をするというもの。高校時代も同じでしたが、3年生の3学期は受験があるので、スキー授業はなしでした。
スキーができる子にとっては、ワクワクする日です。授業が終わると、その場で解散ですが、残りたければ残ってもOKです。当然日が暮れるまで私は滑っていました。
レベルに合わせて4つのグループに分けられます。普段滑る子はいいのですが、滑らない子にとっては、とてもイヤだったと思います。でも、上手ではなくても、それなりに滑る事が出来るのが、当時の「北海道の子ならでは」でした。
今はスポーツの多様化で、冬もいろいろなスポーツをやるために、あまりスキーには行かないようです。私が中学生の頃は、夏の間バレーボールやバスケットをしていても、冬にはスキー部にかけ持ちで入るといった友人もいました。
学校の先生も、スキーの得意な人、そうでない人がいました。もちろん、体育の先生より上手に滑る生徒もたくさんいました。今は、本州出身の先生も多いようで、靴を履くことから教えなくてはならない子もたくさんいて、スキー授業が成り立たないらしいです。
そんな話を聞くと、時代の変化を感じます。昔の方が良かったと言うのは、滑ることが好きだった側の言い分です。年に一度や二度のために、スキー道具一式を買うのはもったいないと言われる事ももっともです。
でも、こんな素晴らしいスキーのできる環境が目の前にあるのに、スキーをしないことの方が、私は「もったいない」と思います。写真は円山(観音山)を真横から見たものです。建物は荒井記念美術館で、私たちが円山で滑っていた当時は、この建物はもちろんのこと、道路すらありませんでした。