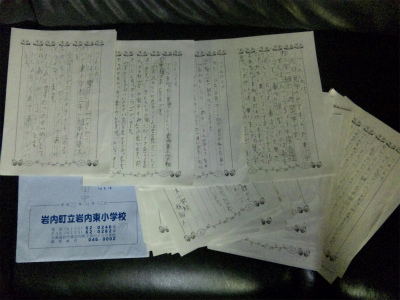9月17日の道新後志版に岩内の銭湯がまたひとつなくなることが記事になっていました。かつて、10軒も岩内には銭湯があったそうです。竹乃湯さんがなくなって、残るのは中央保育所の裏の「みどり湯」とYADA商店となりの「小松湯」の2軒だけです。
岩内は昭和29年の大火の後、町営ブロックと称したアパートが立ち並びました。現在、それらの建物も老朽化となり、新しい町営アパートが建設されるに伴い、人も移動しています。旧アパートは、お風呂がないために、そちらに住む方は銭湯を利用していた人が多いようです。新築のアパートにはもちろんお風呂があるので、銭湯に通うお客さんも少なくなったというのが現状です。
私の記憶では、一八の近くに「浜の湯」というのがありましたね。ここは私がまだ小学生の頃に廃業しました。ボイラーが壊れたのを契機に辞めてしまったと記憶しています。一八に勤めていた女工さんたちもここをよく利用していました。
今は車社会。自宅にお風呂がなくても車は持っている人もいるので、そんな方たちは、円山地区の温泉を銭湯代わりに使っている人もいます。
銭湯と映画館。時代とともに少なくなるのは、何もこれらだけではありません。悲しいことに、岩内の水産加工屋さんの数も急減しているのです。