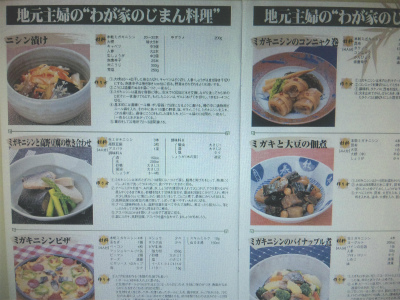八興会館の管理人である、大泉さんからお借りした資料に、『財団法人八興会館 創立30周年記念祝賀会』の記念誌があります。その中には「30年のあゆみ」というタイトルで、創立の昭和38年2月から平成5年の9月までの子供たたちが残した、さまざまな大会での入賞の記録などが載っています。
今日は、その中の一部に昭和40年9月1日発行の「八興会館のあゆみ」より記載してある、館長である紀伊右エ門の昭和38年八興会館落成式のあいさつ文をそのまま転記いたします。
——————————————————————————–
紀 館長 挨拶
一八の商号で皆様から多大のごひいきに預かっております紀でございます。
本日この八興会館の落成式に、ご多用のところわざわざご臨席くださいまして、ご祝詞やご祝儀を頂戴いたし、まことに有りがたく厚くお礼申しあげます。
一八の親爺が、商売に関係のないこのような大それた会館建設などをどうして企てたのか、さぞかし皆様には不思議に思われたことと存じますので、いささか平素感じております一端を申し上げたいと存じます。
池田首相の真似ではございませんが「国づくり」の基礎が「人づくり」であることは申すまでもございません。それには住みよい環境と施設を与えて、明るく楽しい健全な「場」で、次代を担う子供をすくすくと成長させてやりたいということは独り私のみの願いではございません。然るに岩内の町は、教育上よい施設や環境に恵まれているとは、決して申されないのであります。
こういう点から、私は先年も大浜海水浴場の施設に微力ではございますがいささか努力いたしました。また、伝馬船十余艘を備えつけ、これらのご利用に資したり、昨年は円山のスキー小屋の建設にも協力させて頂いたわけであります。
しかし、何と申しましても、年間を通じて利用ができ、かつ日本古来の武道の練磨によることが、肉体と精神の両方向の修養に一番効果があるものと考え、道場の建設を思い立った次第であります。幸い町内有志の方々や、その道の専門の方々のご支援をえまして、昨年11月この会館の建設に着手し、本日落成して開館の運びに至りました。
もとより私は、裸一貫で遠く佐渡より渡ってまいりました風来坊でありまして、何の教養も資力としてございません。従いまして、今後の維持運営や青少年の育成につきましては、全くの素人でわからないわけであります。何卒この上とも、町長さん始め町議会議員、町教育委員会、PTAその他町有志の方々の特段のご支援とご指導を仰ぎまして、この会館がますます充実され、青少年の健全な育成に多少とも寄与できますことを祈念する次第であります。
本日は私の多年の夢の一端が現実しました喜びと感謝の気持ちを申しあげましてお礼のご挨拶といたします。まことにどうも有りがとうございました。
 バックナンバーはこちらから
バックナンバーはこちらから
その1
その2
その3
その4
その5
その6





 バックナンバーはこちらから
バックナンバーはこちらから