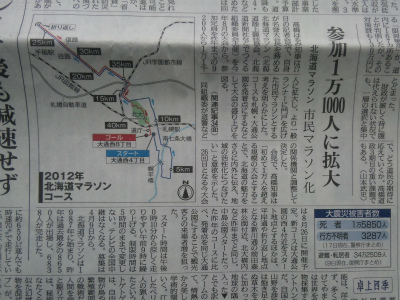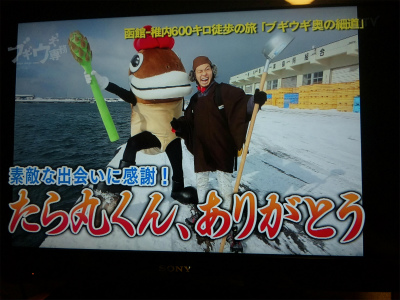昨年12月より日曜日は、岩内のスキー場のことを中心に書かせていただきましたが、今回が最後となります。来週からは、またマラソンのお話に戻りますが、最後に私自身のスキーについて書かせてください。
さて、ずっとこのブログを読んでいる方は、私がスキーが好きだと言う事は、うすうす感じられたことでしょう。スキーに行きたくて、夏の小遣いを使わずにため込んで、冬のリフト代につぎ込むという子供でした。
小学6年生の時には、一人で岩内から倶知安までバスに乗り、倶知安でヒラフ行きのバスに乗り換えて、ヒラフスキー場に行って滑ったりしていました。ひらふスキー場行きのバスは、まだワンマンカーではなく、切符を一人ずつ車掌さんが売りに来る時代でした。
小学生が一人でバスに乗っているのです。若い女性の車掌さんは、そんな小学生の私に「一人で来てるの?」と質問して、「うん」と答えると、切符を切ったふりをして、お金を取らなかったのです。何回か行くと顔も覚えられました。とっても嬉しかった思い出です。
ほとんどの人が、学生を卒業してスキーを引退。子供がスキーを始めるようになって、再開する人が何人か。私はずっと続けていました。何が魅力かは、自然の山を相手にするからです。同じコースであっても、行く時によっては、雪質がまったく違います。いろいろな雪、いろいろな斜面、それらは、経験を通して少しずつ上手に滑る事が出来るようにります。他のスポーツでは足手まといになる少年が、スキーだけはそんな経験を積んで、一人前になっていきました。
このブログでは、岩内のスキー場について書きましたが、現状のリフト1本のコースでは、ある程度のレベルの人たちにとっては、物足りないコースです。ゆえに、地元子供たちのためのスキー場とキャットを使って深雪を堪能できる二つの顔を持っています。
そんなことから、私のホームゲレンデは、ひらふスキー場です。世界から人が集まるそのゲレンデは、ナイターではその規模は世界一です。その世界一がすぐそこにあるのですから、利用しないのは、もったいない。
岩内町でラーメン屋をしている高校の同級生のT君、70歳を越えても元気な事務機屋Aさん、30代の同業者のK君と仕事を終えてから、ひらふへ。2時間ほど滑って、ワイス温泉に入って、岩内に戻って軽く一杯。今日の雪は良かったなぁ~などと言いながら、過ごすひと時はとても幸せです。
近くでそんな気持ちに共感される人がいましたら、私たちとひらふスキー場でご一緒しませんか?上手下手は関係ございません。スキーを楽しむその気持ちがあれば、OKです。