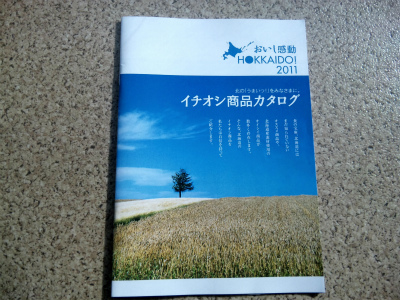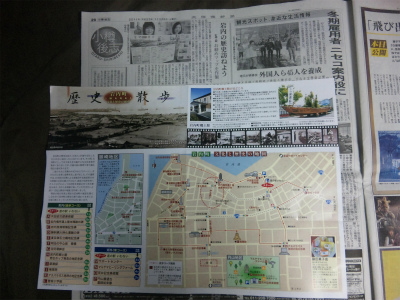赤い消火栓も冬対策をしています。消火口のところから、ぞうさんの鼻のように、上に伸びています。最初はなんぞや?と思っていましたが、雪が降り積もると納得がいくのです。(真冬の状態は、こちらです)
場所によっては、ほっておくと、上に伸びた口までもふさがってしまうため、消防の人たちは、定期的に巡回をして、消火栓周辺を除雪しています。岩内のいたるところにある消火栓。大火を経験し、火に対する気構えは他の自治体に比べると意識が高いように感じます。
いつも思うのですが、ちょっと遊び心を使って、顔を書いたりしたらダメでしょうか?いろいろな表情の顔などを作って、どこにどんな顔があるとか、動物の体の一部を想像させるとか、いろんなお楽しみがあってもいいのじゃないかと思います。
私は最近の子供が外を歩かなくなっているのを憂慮しています。消火栓を使う時は、必死なときだから、そこに遊び心を入れるなんてけしからんと言われてしまうかもしれませんが、一つの提案としていかがでしょう?