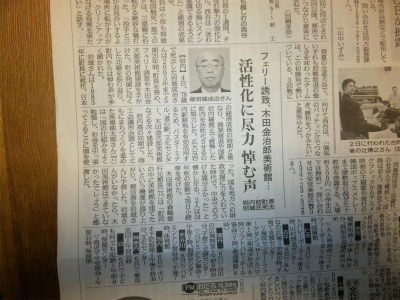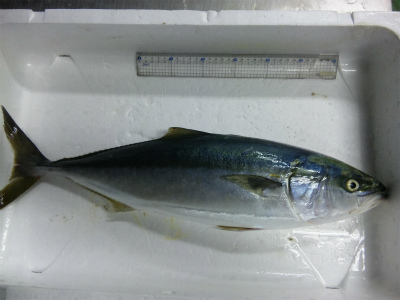マラソン大会に出る皆さんは、いつもスタートの時、どの辺に並びますか?
小さな大会で、ブロック分けされていない時は、それぞれが自然に立ち位置が決まるように感じます。速い人は、スタートラインから数列目。それなりの人は、後方に立つといった具合ですね。
洞爺湖、千歳などの参加者の多い大会は、自己申告で、3時間以内、4時間以内、5時間以内などの区切りがあって、そこに並びます。私が参加するハーフマラソンで区切りを付けるのは、札幌マラソンくらいでしょうか。めちゃくちゃ人が多いですものね。
この札幌マラソン、500人単位で、区分けされます。前年のこの大会の記録をもとに速い人順に番号がつきますが、最初は陸連登録者です。そのあとに、一般登録者の速い順となります。北海道マラソンのように、2年以内の他の大会の記録は使えないのです。
私が最初に参加した年は、一番最後のブロックからのスタートだったので、ロスタイムがかなりありました。翌年は第2ブロックからのスタート。翌々年は第1ブロックに入る事ができました。しかし、近年陸連登録者が多くなり、一般参加者である私は、今年はとうとう第二ブロックに押し出されてしまいました。
まぁ、しょうがないですね。スタート位置が下がる事で、ロスタイムが増えますが、登録してまで記録がほしいというものでもないので、決められた通りにいたします。
毎年、移動するときに、後方の方がどさくさにまぎれて、どんどん前に出る方がいます。また、スタート後に歩道や対向車線を走らないようにアナウンがされてもやってしまう人がいます。人の多さで、抜くことができなくてイライラする気持ちもわからないではないですが、マナーは守って走りましょう。どうしても前に出たければ、陸連登録して走られる方がいいですね。
言い忘れました。札幌マラソンは女子は右側の前方に並びます。男性よりは、ちょっとお得になっています。
ということで、本日は第36回札幌マラソンです。前に出たいと言うのであれば、整列開始と同時に、指定されたブロックの前に並びましょう。くれぐれも申しますが、前にでたからと言って、その分結果がついてくるものではありませんよ。今までの練習が今日の結果となるのです。
私は今年最後のハーフマラソンです。結果報告は来週いたします。写真は読売新聞に掲載された、昨年のスタート風景です。