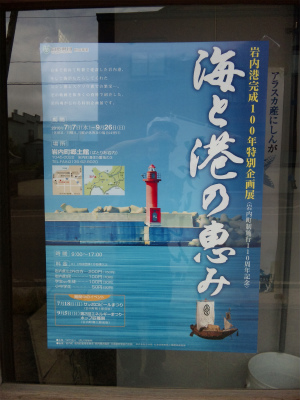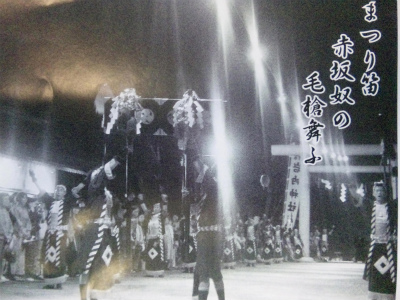大豆を使わず、ニシンを発酵させて作った味噌状の発酵調味料『にしんのおかげ』。今日は私の奥様が腕によりをかけずに作ったマカロニサラダをご紹介。
マカロニと春菊。冷蔵庫に残っていたものを使います。特別に買ってくる必要はございません。『にしんのおかげ』とマヨネーズを混ぜます。このマヨネーズと『にしんのおかげ』の配合比率はお好みです。ゆでたマカロニと春菊にそのマヨネーズにしんのおかげをまぜるだけで出来上がり。超簡単レシピ。これなら「奥様もう一品」に採用されるでしょうか。
要するに、普通のマヨネーズだけの味でなく、『にしんのおかげ』を混ぜることによって、いつもと違う味を演出できます。さらにイノシンサン系のうまみがあるので、味にうるさい旦那様にちよっとパンチを食らわせることができます。欲を言えば、アミノ酸系すなわち、昆布系のうまみが加われば、ダブルパンチがトリプルパーンチ!になります。
やってみて、パンチが利かなかったら・・・・ごめんなさい。でも大丈夫です。きっと奥様の勝ち。