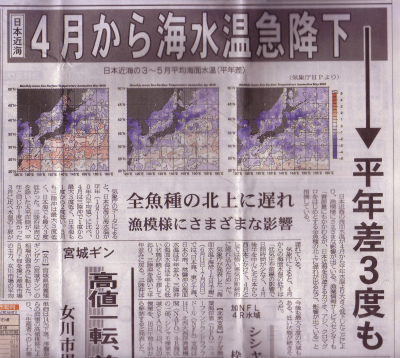札幌市の狸小路5丁目に道産食彩HUGマートというお店があります。道産食材の直売店です。ここに、一八の「にしんのおかげ」と「めんこちゃん」が売られています。
生鮮食品もあるし、加工食品もあります。またHUGイートでは、屋台風に11店が営業していて、道産の美味しいものがたべることができます。ちょっとのぞいてみると楽しいですよ。スタッフの方たちは、商品陳列に朝から大忙し。元気な声で「いらっしゃいませ~」と活気があります。
狸小路といえば、札幌の大通とすすきのの中間に位置して、1丁目から7丁目までアーケードになった商店街です。歴史もありますね。私たちの年代では、TVCMの「ぽんぽこ~、さっぽろ~、ぽんぽこ~~、た~ぬ~き~こ~~じは・・・・・・・」というテーマソングを思い出します。一時は客足が遠のいて大変だというお話もありましたが、今は国際色豊かな客層と、ホテルなどの昔の商店街では考えられない建物まであります。お近くに行きましたら、狸小路に足を運ばれ、5丁目HUGマートを覗いてみてはいかがでしょう。